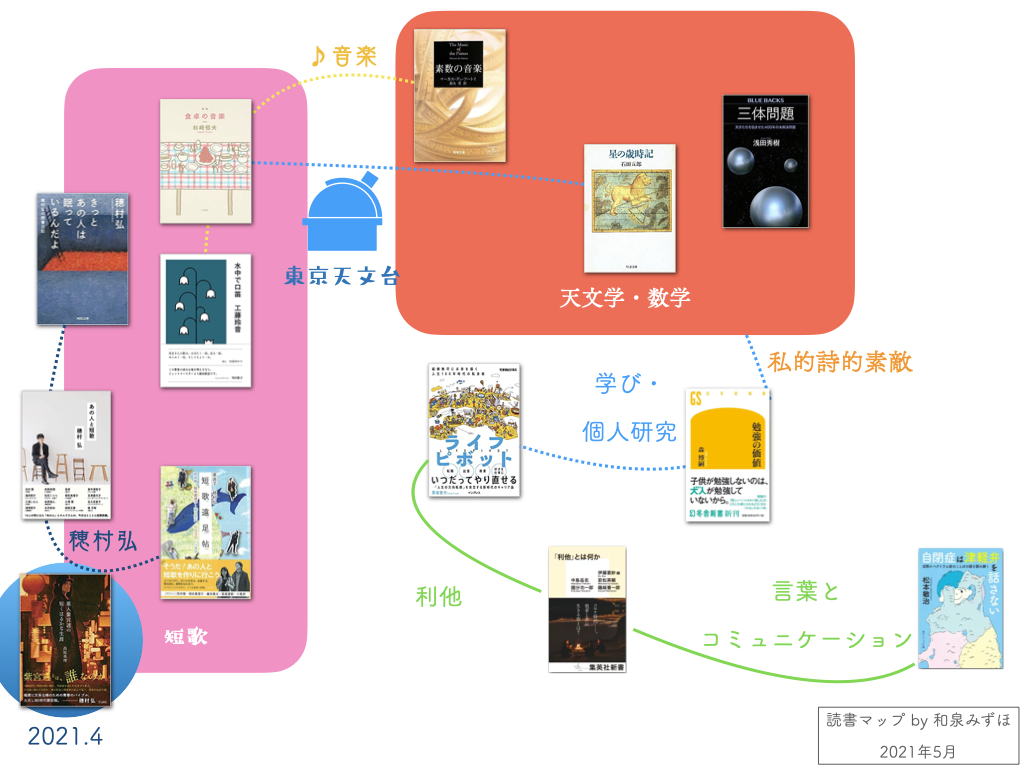2021年7月の読書マップです。

スタートは2021年6月の読書マップから「藤井聡太論」。7月も将棋タイトル戦を連戦連勝、藤井聡太さんの勢いが止まりません。
いっぽうで王座戦挑戦者決定戦は「受け師の道」木村一基さんと将棋連盟会長の佐藤康光さんという組み合わせになったりと、40・50代棋士の活躍も見どころ。
この本から、河口俊彦「一局の将棋 一回の人生」をつなげてみます。
時代は昭和のおわりから平成のはじめ、羽生善治さんや佐藤康光さんなどがプロデビューしたころ。
自身も棋士である河口さんのエッセイは生々しい時代の空気をとらえ、のちに平成の将棋界を席巻することになる〈羽生世代〉の強さに半信半疑だったというのが今では信じられないかもしれません。
棋士によって指される何十、何百という対局と、「一回の人生」を対比させる描き方も読み応えがあります。
続けて、さまざまな人の〈生き方〉を感じとれる本が先月は印象的でした。
「若ゲのいたり」はご自身もゲーム会社に勤務していた漫画家・田中圭一さんによる対談マンガ。
「ファイナルファンタジー」や「ぷよぷよ」などの有名ゲームに携わったクリエイター、「MOTHER」を作った糸井重里さんなど、ゲームに人生をかけた人々の情熱が伝わります。
「須賀敦子全集」は若松英輔さんの「読書のちから」の本で知った『ミラノ・霧の風景』『コルシア書店の仲間たち』などが収録されています。
イタリアで暮らし、書店仲間と共にあった著者の、優しく、ときに哀しげな文章が心にのこります。
「本のエンドロール」は印刷会社を舞台に、出版業界の内幕を描く安藤祐介さんの小説。
ときに無理難題を押しつける編集者や著者に振り回されたり、電子書籍に複雑な思いを抱く印刷工と経営層の対立があったり、「紙の本が好き」という人にも「電子本も良い」という人にもおすすめしたい本でした。
今回は紙の本で読みましたが、電子だと「エンドロール」はどうなっているのでしょうね?
電子化に積極的な作家と言えば森博嗣「お金の減らし方」。趣味の庭園鉄道を実現させるためのアルバイトに小説を書いたと公言する森さんらしく、独特の調子で、お金の増やし方ならぬ減らし方を指南します。
「毎日は笑わない工学博士たち」は、そんな森さんの作家デビュー直後のブログを書籍化したもの。このシリーズは幻冬舎から全5巻刊行されています。
まだ某国立N大学に勤務されていて超多忙、毎月のように東京出張に行く森助教授(当時)の日常は、いろいろな意味で今読み返すと隔世の感があります。
科学者でもありエッセイストとしても知られた戦前の作家と言えば寺田寅彦。角川ソフィア文庫「科学と文学」はKADOKAWAの株主優待でした(笑)。
映画や連句といった芸術に共通する構造を分析したり、文学を科学者の観点から語るエッセイには、今でもいくつもの新たな発見があります。
井上夢人「魔法使いの弟子たち」は電子で以前に買ったまま、たまたま読んだら、おそるべきパンデミック小説でした。
謎のウイルス性疾患〈竜脳炎〉の感染が拡大した世界。奇跡的に恢復した主人公たち三人には、信じがたい異能力が備わっていた…
寺田寅彦の言葉を借りれば「実験としての文学」の想像力を感じます。
ここからは科学本。カルロ・ロヴェッリ「すごい物理学講義」は先月の「アインシュタイン方程式〜」でいえばタテガキの物理本ながら、哲学や文学のようにも読める名著。
作中の、科学は不確かだが「目下のところ最良の答えを教えてくれる」という言葉が胸に沁みます。
地学本の注目は「日本列島の『でこぼこ』風景を読む」。複雑に入り組んだ日本列島の成り立ちをひもとくことで、ランドスケープとしての日本の美しさを再発見できます。
そして「まっぷる」シリーズで知られる昭文社からも、「愛知のトリセツ」のように各都道府県の地理・歴史を解説した本が続々と登場しています。
地元や好きな県の本を手にとってみると、意外な発見があるに違いありません。
そしてまた、さまざまな場所に行ける日が来ることを願って。