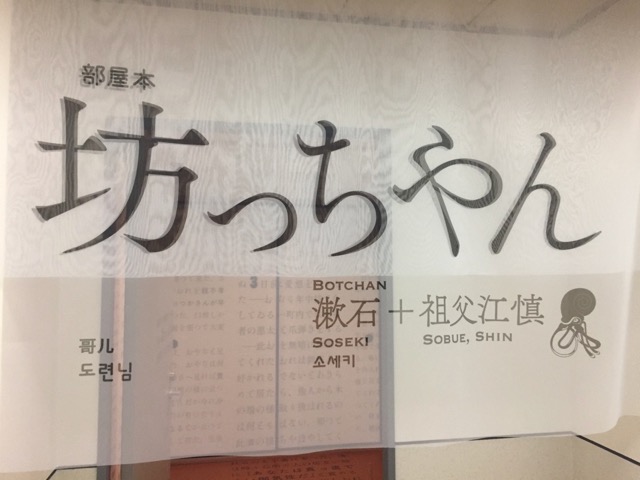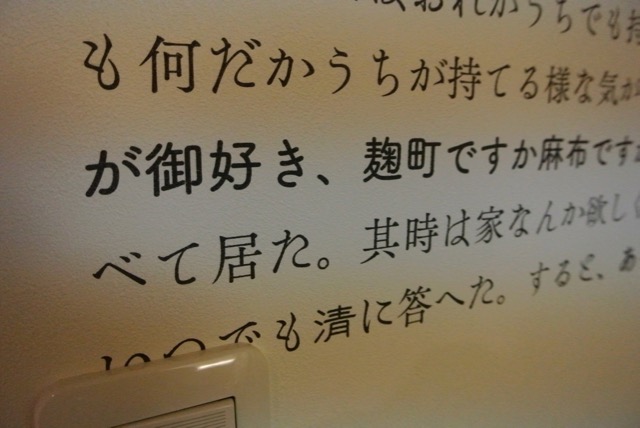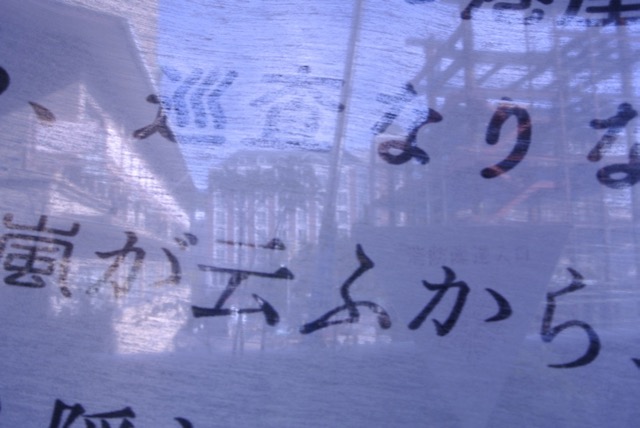いまさらですが、このブログ「凪の渡し場」は、「日常に新たな視点を」をコンセプトに、さまざまな世の中の楽しみかたについて提案しています。
では、実際に新しい視点を見つけるにはどうしたらいいのでしょうか。
ひとつの方法は、これまでいろいろな記事で紹介している、さまざまなものの知識を身につけることです。
フォントの名前であったり、路上にあるものの名称(たとえば、パイロンであったり、建築材であったり)をおぼえることで、これまで区別していなかったもの、気にもとめていなかったことに目を向けるきっかけになります。
でも、それはあくまで、新たな視点を身につける補助線にすぎません。
ほんとうに大切なことは、知識そのものよりも、それを見ようとすること、観察することにあります。
そんな観察の習得方法について書かれたのが、その名も「観察の練習」という本です。
この本の本編は、まちなかのさまざまな日常の風景を切り取った写真だけのあるページと、それについて書かれたページに分かれています。
写真のページで、日常の風景から著者が感じた「小さな違和感」は何かを考えてからページをめくることで、それが自分の思ったことと同じかどうか、あるいはまったく違うことが書かれているかを楽しむことができます。
もちろん、ひとりひとりの視点はすべて違うものだから、その観察結果に「正解」はありません。
その違いが、もともと自分がどのような視点をもっているのか、何に注目しがちなのか、そんな思考のクセをつかむヒントにもなるかもしれません。
また、この本自体が、表紙に書かれたタイトルの漢字が部分的にしか白塗りされていなかったり、本編も一部内容に合わせて特殊な文章の組み方がされていたりと、小さな違和感を楽しむことができます。
実際にどんな「観察」が紹介されているか、気になる方はぜひ本をお読みいただくとして(この記事のアイキャッチ画像の謎も、本を読めばわかります)、今回は「凪の渡し場」オリジナルの「観察」をしてみます。
さて先日、とある博物館を訪れた際、こんなパイロンを見かけました。
「街角図鑑」を買ってからというもの、パイロンを見つけては撮るということをしているのですが、よくよく考えると、わざわざパイロンの形状にぴったりな「開館」の看板をかぶせているのはとてもふしぎです。
いわゆるサンドイッチマンならぬ、サンドイッチパイロンです。
ちょうど建物の一部が工事中だったため、工事現場を囲むパイロンがあり、訪れた客が閉館中だと間違わないように「開館」をかぶせたのかもしれません。
けれど、同時に、近くの駐車場で、こんなパイロンも見かけました。
契約車両以外の駐車を禁じる看板がわりに使われています。
よく見ると、こちらのパイロンも先ほどのパイロンも、上部以外の三方に囲みがあり、真ん中に紙やプレートを入れられるようになっているようです。
ここまでくると、工事中かどうかは関係なく、パイロンを手ごろな看板がわりに使おうとする意志を感じます。
たまたま、ここの関係者がその用途に気づいたのか、あるいはパイロン業界でひそかに普及しているものなのか…。
こんなふうに、自分でも撮りためた写真を見返して、さらに深く観察することで、そのときは気づかなかった視点を楽しむことができます。
もちろん、まだ路上観察に慣れていない人も、ぜひ街に出て、さまざまなものを観察して、写真に撮ってみてください。
最後に、この本に近い「観察」を楽しむ本として、こちらも紹介しておきます。
主に、街ゆく人々が無意識にとった行動を写真におさめ、発想の仕方やデザインの考え方を学ぶ本として、工学博士で作家の森博嗣さんが翻訳されたことでも知られます。