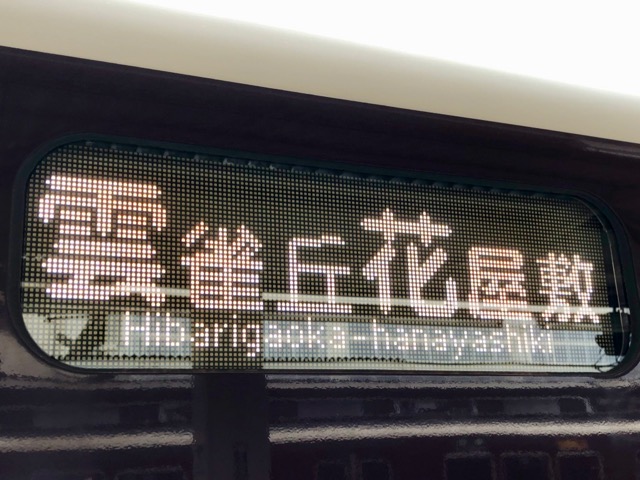※この記事は約一年ぶりの〈広島偏愛シリーズ〉です。
広島に行くと、必ず食べるご当地料理があります。
それは、いわゆる広島風お好み焼きです。
大阪のお好み焼きとは違って、焼きそばやうどんを入れて焼く特有のスタイル。
オタフクソースをはじめとする、濃厚ソースの味付け。
お店ごとに異なる、さまざまな具材や味付けなどのオプション。
そんな個性的な食のスタイルが街中に浸透している広島は、全国各地を旅して見てきた中でも珍しい存在です。
(名古屋のいわゆる喫茶店文化も、それに近いものがありますが)
いったい何故、広島だけにこのようなお好み焼文化が存在するのか。
それを紐解く、〈お好み焼ラバーのための新教科書〉を銘打った本があります。
※「凪の渡し場」では、いままで〈お好み焼き〉〈広島風お好み焼き〉と表記してきましたが、これ以降は本書に従い〈お好み焼〉〈広島お好み焼〉と表記します。
レストランレビューサイトを運営している著者の調査により、お好み焼の発祥から現在にいたるまで、そして名店といわれるお好み焼屋の数々が紹介されていきます。
意外にも、お好み焼のルーツは明治から大正にかけての東京にあるといいます。
この料理はそこから東海道・山陽道をたどるように広まり、そして戦後の復興とともに大阪や広島で独自の進化をあゆみます。
さまざまな店主やその先代のエピソードから、広島というまちの歴史が浮かび上がります。
食の歴史は、ひとの歴史でもあるのです。
また本書では、地元でよく出される、ヘラと呼ばれる小さなコテでお好み焼を上手に食べるコツも紹介されています。
多くの具材が層状になっている構造上、うまく切り分けるのにもなかなか苦労することがあります。
慣れた手つきで食べる地元の方にひそかな憧れをいだいていたので、次に広島に行くときまで、この本を読んで予習しておきます(笑)。