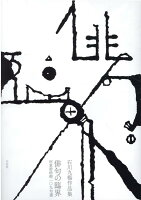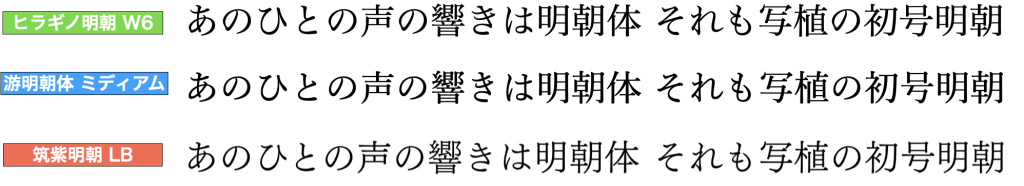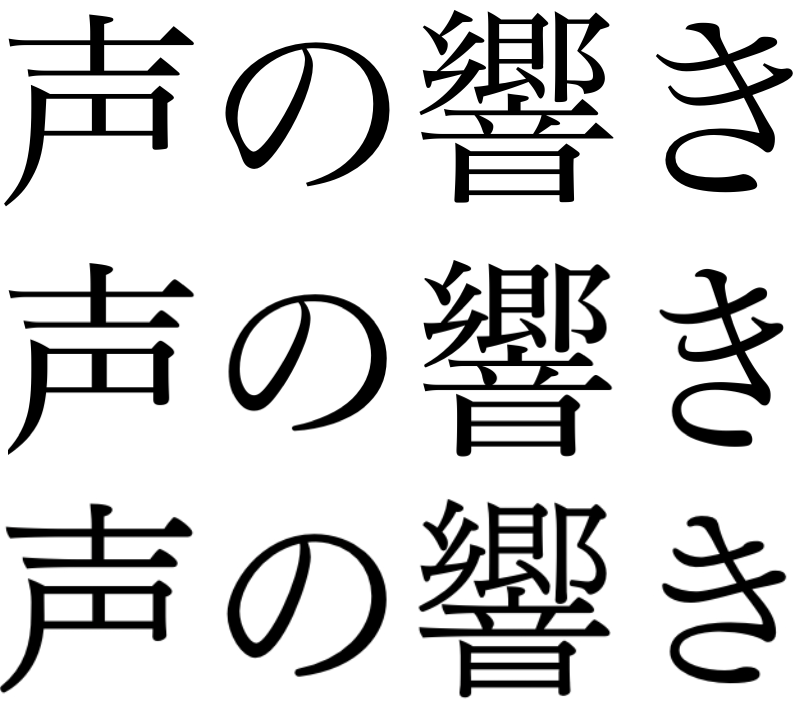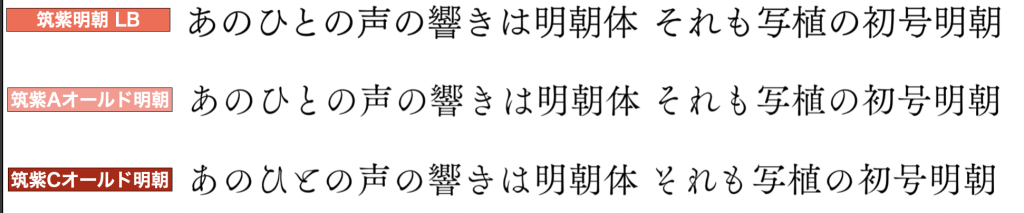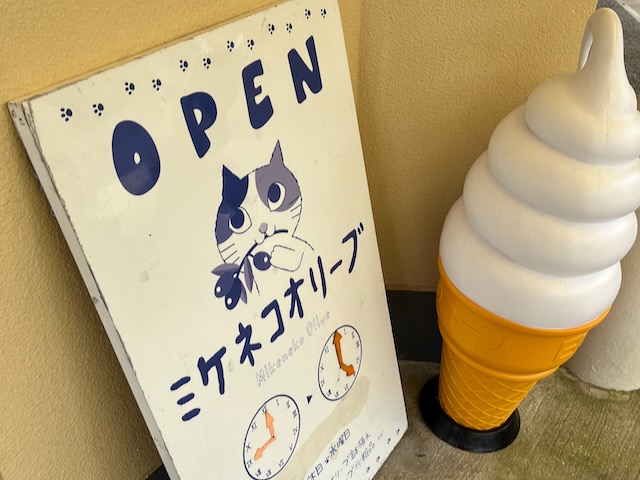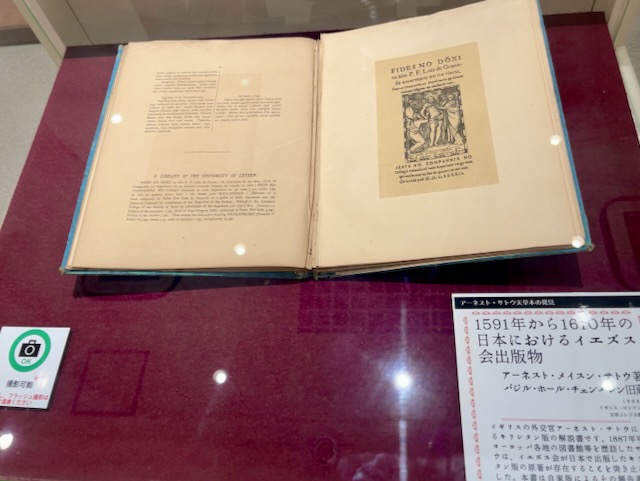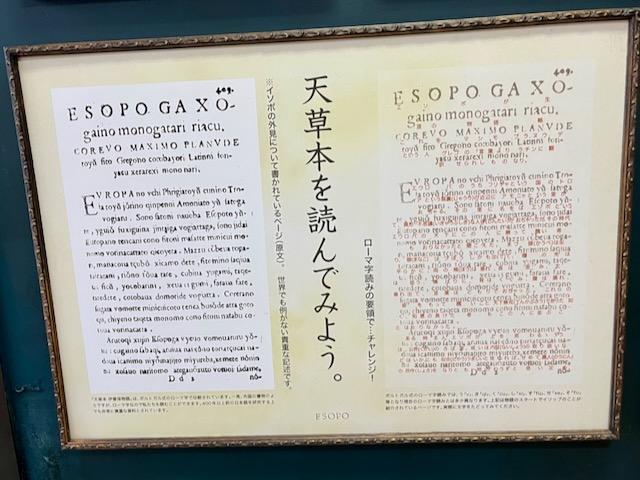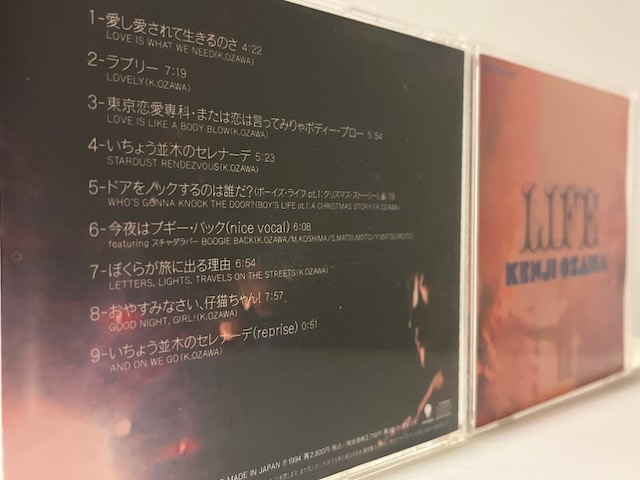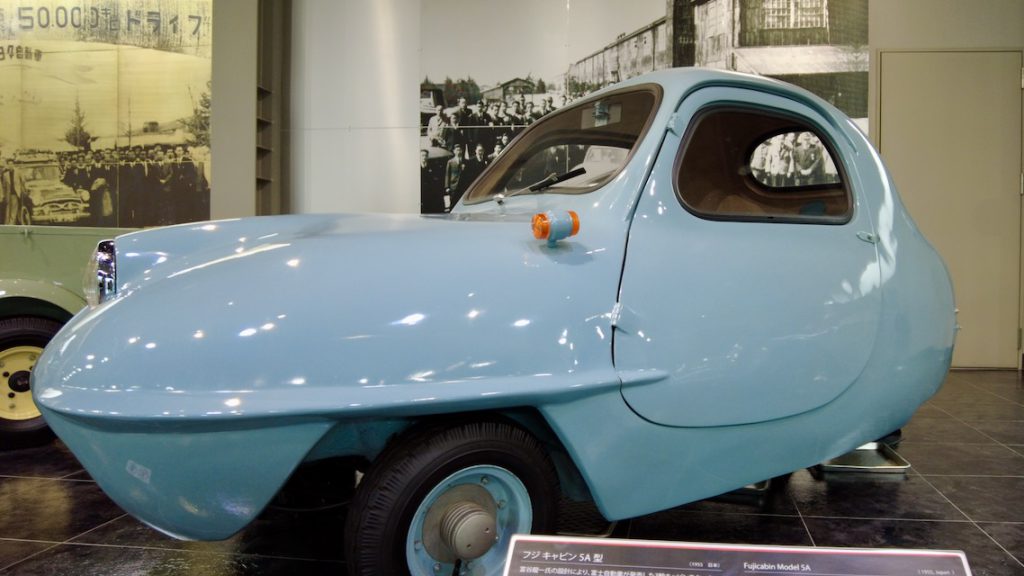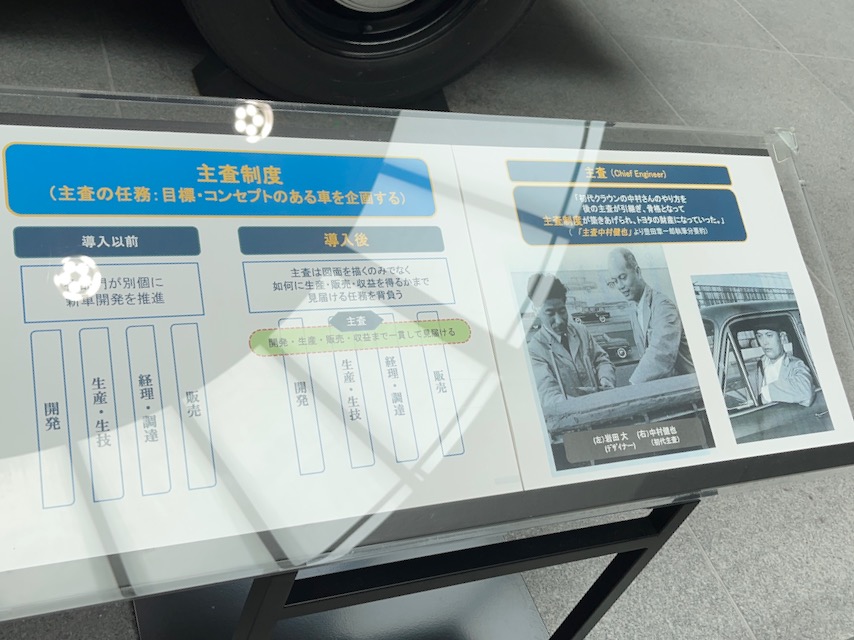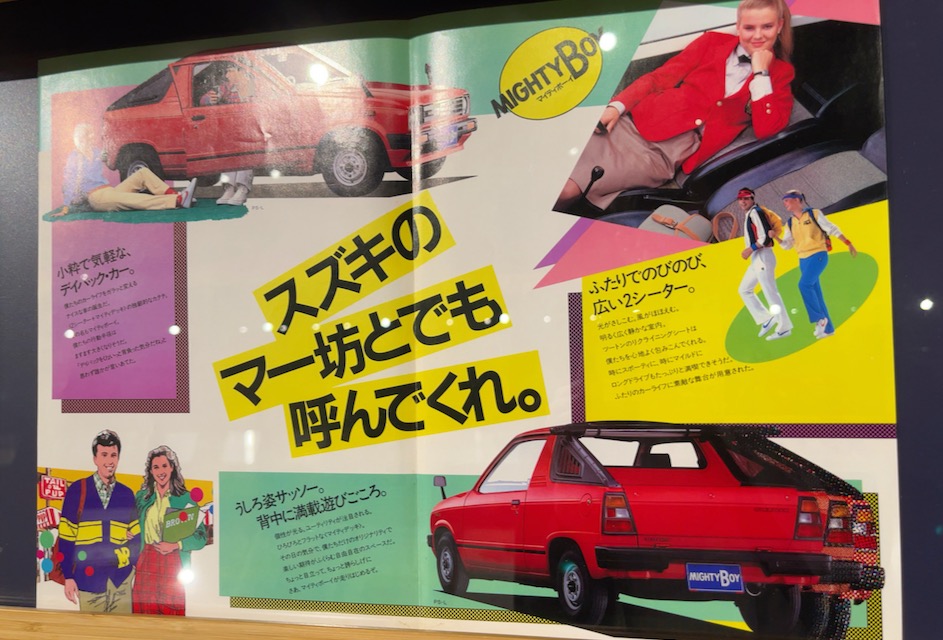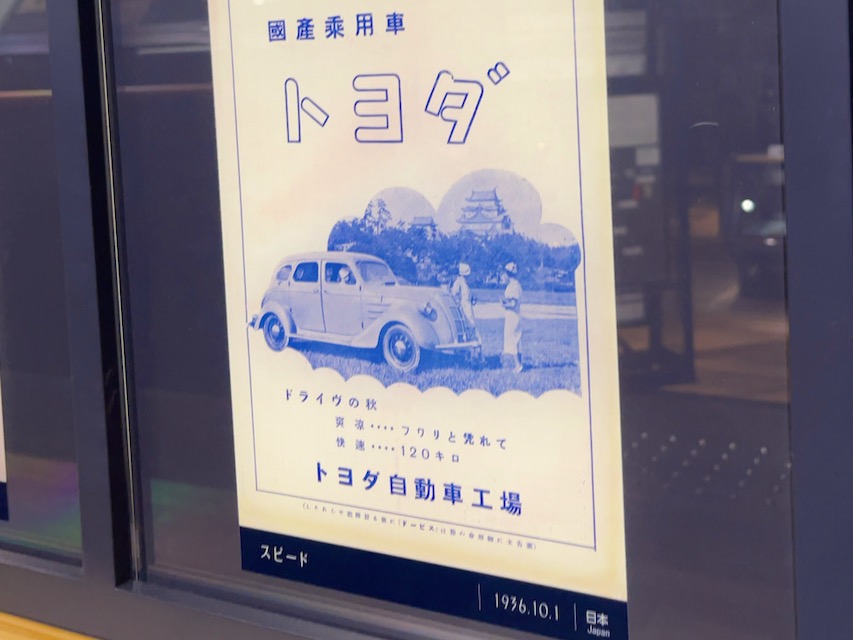2024年も、さまざまなアートイベントや展覧会が開催されています。
今回は東京・上野から、ふたつの美術館をめぐります。
広大な敷地をほこる上野恩賜公園。
美術館や科学館、動物園などが立ち並び、すべて回ろうとすれば、一日あっても時間が足りないくらいです。
〈凪の渡し場〉的には、屋外の看板に注目した文字さんぽも楽しめます。

丸ゴシックの「ボート場」とイラストがかわいい。

これは象のおしりをモチーフにした看板でしょうか。やはり丸ゴシックが大活躍。
でも、きょうのお目当ては動物園ではなく、上野の森美術館「石川九楊大全 言葉は雨のように降りそそいだ」です。

文字やフォントに関する著作も豊富な書家・石川九楊さんの大規模展覧会です。
前後期で展示替えがあり、古典を中心とした前期は残念ながら予定が合いませんでしたが、後期【状況篇】も、いわゆる「書道」という言葉からイメージする枠組みにとどまらない作品が目白押し。
一室を埋めつくす85mの大作「エロイエロイラマサバクタニ又は死篇」などに圧倒されて館内を進んでいくと、個人的に感動の作品に出逢えました。
それが、自由律俳句で知られる俳人・河東碧梧桐のことばを書として再構築した「俳句の臨界 碧梧桐一〇九句選」。
館内は撮影禁止ですが、美術館前のポスターにも作品が使われていました。

句は「ざぼんに刃をあてる刃を入るる」。
ひらがなの〈ざぼん〉を取りかこむ肉厚のザボン。
その皮と種までが墨の濃淡で表現され、鋭利な刃物があたっている一瞬が切り取られます。
碧梧桐の句自体がおもしろく、さらに石川さんの書による表現が重ね合わされ、時間を忘れて楽しめました。

最後は写真撮影可のコーナー。有名な新潟の日本酒「八海山」の文字も石川さんによるものだったのですね。
しかも普通酒ではなく高級な大吟醸酒というところが心憎い。

さて、上野駅に戻ります。
高架下では「最も画数の多い漢字」として有名になったビャンビャン麺も売られていました。
とはいえ列車の時刻が迫っているので駅構内へ。構内にもそこかしこに動物のキャラクターが隠れています。

しかし、案内に従って階段を降りると、なにやら雰囲気が一変します。


まるで令和から昭和にタイムスリップしたような14番ホームです。

上野発の夜行列車、ではなく昼行特急「草津・四万」で群馬へ向かいます。
「四万=しま」と読み、四万の病を治すと言われる四万温泉が由来だそう。
今回は伊香保温泉の最寄駅でもある渋川駅で下車します。

駅名標が筑紫A丸ゴシック!
観光SLの停車駅ということで、黒字に金のSL色ながら、単なるレトロ趣味にとどまらない、かわいさ抜群の演出です。
ちなみにこの夏は「SLぐんまちゃん号」が運行されるとのこと。

帰りに寄った途中駅の高崎駅も〈ぐんまちゃん〉にジャックされていて、こちらもめちゃめちゃかわいい。


改札にもぐんまちゃん(渋川駅ではなく高崎駅です)。

渋川駅でやってきたバスまでぐんまちゃん。

グリーン牧場前のバス停で下車します。ここも動物のキャラクターに彩られ、期せずして動物づくしの旅となりました。
それでも、向かうのはグリーン牧場ではなく、おとなり原美術館ARCです。

品川にあった原美術館が、ここ群馬県渋川市の別館〈ハラ ミュージアム アーク〉と統合して新しく誕生した美術館とのこと。
都心とはまた違って、広い敷地に分散する展示室を自由にめぐりながらアート作品を楽しめます。
現在は「日本のまんなかでアートをさけんでみる」展を開催中です。
日本のまんなか…?
総務省も認める日本の真ん中といえば、人口重心地の存在する岐阜県では?
https://www.stat.go.jp/info/guide/pdf/gifu.pdf
などと中部民としては思ってしまいます。
けれど、どうやら渋川市も、日本の主要四島の最北端・宗谷岬と最南端・佐多岬を円でむすんだ中心に位置する「へそのまち」宣言をしているのだそう。
さらに言えば兵庫県にも、日本標準時である東経135度を通る「日本へそ公園」があるなど、〈まんなか〉という概念はとらえかたによってうつろいうるものでしょう。
そんな中心と周辺を、振り子のように行き来することが、まさにアート的思考かもしれません。
さて、展示です。作品のいくつかは写真撮影可能。

とりわけ目をひいたのが、奈良美智さんの「My Drawing Room」。
以前の原美術館にあった展示を移築・恒久化したものだそう。
仕事部屋のような、子供部屋のような空間には、そこかしこに仕掛けがほどこされ、見飽きません。

屋外には、アンディ・ウォーホルの巨大なキャンベルトマトスープ缶が。

そのとなりのカフェスペースで、展覧会記念の日本列島ケーキをいただき、夏の暑さを乗りきります。

ピンクのおへそがかわいい。
思いきりアートをさけぶ、日本の夏でした。